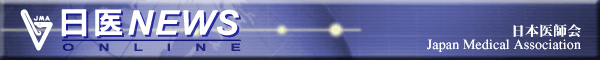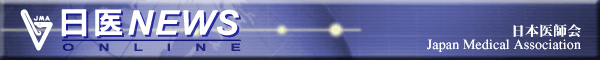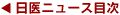 |
第1095号(平成19年4月20日) |

勤務医中心の医師会へ〜「立ち去り」か「参加」か〜
古川俊治(医師・弁護士)

「立ち去り」を余儀なくされる勤務医の労働環境
勤務医の労働環境は,厳しさを増す一方である.勤務医の過労死や過労自殺事例が多数報道されているが,その給与は低く抑えられたままである.
近年,勤務医の労働環境が悪化した主な原因としては,(1)医療機関の経営状況の悪化(診療報酬抑制,建て替えや新機器購入のための資金需要の高まり)(2)医療安全の要求の高まり(医療安全のための業務負担の増加,医療従事者の民事・刑事責任の厳格化)(3)臨床研修必修化等に伴う医師の獲得困難(特に地方,重責診療科において格差が顕著)などが挙げられる.
そのため,小児科,産科,麻酔・外科系など,少なからぬ診療科で,勤務医が耐え切れなくなって職場から立ち去りつつある.その結果,残された勤務医の労働環境はさらに悪化し,次の立ち去りを余儀なくされているという悪循環が続いている.
日本の医療費は高いのか?
医療費削減政策の大前提は,国民医療費が過大に膨張しており,大きな制度変更を行わなければ,近い将来,必ず財政破綻を迎えるという推測である.しかし,厚生労働省の医療費の試算は,今まではるかに過大に見積もられてきた.厚労省は二〇〇六年現在,二〇二五年度の医療費を六十一兆円と推測しているが,一九九五年には同年の医療費を倍以上の百四十一兆円と試算していた(図).長期の推測は,成長率等の仮定を少し変えるだけで,実態から大きく外れた虚像を作り出す.現実より過大な推計数字に基づいて医療費削減がなされると,医療の質や安全という問題が起こらないか,当然,問題となる.
実際には,医療費は喧伝されているほどには増えていない.先の医療改革の議論直前の六年間(一九九七年度から二〇〇三年度)では,国民医療費の増加は総計で九%,年平均一・四五%増(ただし,介護保険施行による一・八%減を含む)に過ぎない.誇張されがちなのは,対GDP比が大きくなっているからであるが,対GDP比が上昇した理由は,デフレによってGDPが縮小を続けたことにもよる(一九九七年度五百二十兆円に対し,二〇〇三年度五百一兆円).医療費用の過半は人件費であり,最も低下し難い.そのため,対GDP比が大きくなったわけである.
周知のごとく,日本は先進国で最も安いコストで,世界最高の医療の質を達成している.しかも,これを出来高払い制度の下で実現してきたというのは,日本の医療従事者の高い職業倫理の賜物と考えられるのであって,この点は欧米の多数の識者が一致して認めてきたことである.
英国では,サッチャー政権下の医療費削減政策の結果,医療機関受診のための待機患者リストが膨大な数に上り,国民医療の質が著しく損なわれたことはよく知られている.厳しい労働条件に耐えかねた医療従事者は,一九九五年から五年間で,何と二六%が海外へ流出して深刻な人手不足となり,医療従事者の士気は低下し,医療事故が多発した.ブレア政権下で医療費増額の政策へ転換し,二〇〇五年には対GDP比で日本を抜いた.医療費削減政策を進めようとしている現在の日本は,英国の失敗に,何を学んでいるのであろうか.
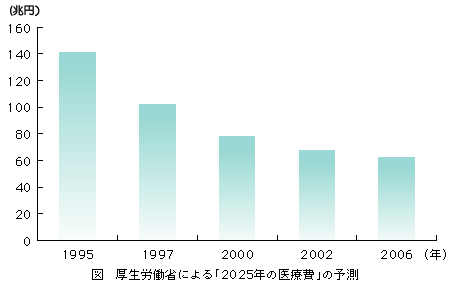
医療従事者を罪人にしても医療は良くならない
一方で,医療安全に対する要求は一段と厳しくなった.特に目を引くのは,近年の医療従事者に対する刑事制裁が頻繁に問題とされるようになったことである.昨年の福島県立大野病院事件も大きな話題になったが,医師が逮捕される事件もまれではなくなった.
本来,法律上の過失を問うためには,行為者に結果の予見可能性と回避可能性が存在する必要があるが,不確実性を本質とする医療行為においては,そのいずれもが欠けていると思われる場合が少なくない.それにもかかわらず,刑事制裁の脅威の下に置かれるのでは,必要性の低い検査を行う保身医療や,積極的治療を控える萎縮医療に陥るのみである.専門的判断が必要な医療過誤事件については,民事責任と行政処分で対応するのが合理的であり,米英では医療過誤に対する刑事制裁は,ほとんど行われていない.
また,医療の安全や質の向上には,新しい機器を導入したり,人員を増やして業務の繁忙を緩和していく必要があるが,そのためには,当然多大なコストが生じる.医療費を削減するなかで,医療安全や医療の質の向上を主張しても,建前だけの空論となりつつある.
選択の時─勤務医が中心となって正論を伝えよう
問題なのは,国民の間に医療が効率的に提供されているという認識が薄く,いまだ医療への投資の合意を得る状況に至っていないことである.これには,「薬漬け・検査漬け」「医師の高収入」など,マスコミの報道によって実態から遊離したイメージが作り上げられてきたことが大きい.
ただ,一方で,マスコミは,勤務医が過酷な労働環境を強いられ続けた結果,地域医療が崩壊の危機にさらされていることに,ようやく気付き始めてもいる.勤務医救済に対する国民の理解を促し,これを医療への投資の契機とすることが非常に大切である.
費用削減を至上命令とする行政側には,医療側を一層安価にうまく利用しようとする基本的な動機がある.このような状況で,勤務医の生活を,一体だれが守るのであろうか? 学会のなかやマスコミを通じての反論にとどまる限り,行政側は無視が可能である.
勤務医が,患者のために医療現場を改善するとともに,自らの職場環境を改善していくためには,自らが政治的実効力を発揮していかなければならないことは,民主主義の原理の下では自明の理なのである.
今までも,「勤務医のための組織が必要である」との主張は数多く耳にしてきたが,残念ながら,勤務医自身による,そのための具体的努力はほとんど見られなかった.実態としては,開業医・管理医が活動の中心である日医が,間接的ながら勤務医の利益を擁護してきたわけである.一方で,国民一般から見れば,開業医も勤務医も「医師は医師」に過ぎず,両者の確執は,国民の医療不信を募らせるだけのことである.結局のところ,勤務医自らが現在の不合理な労働環境を変えるために取り得る唯一の現実的で実効的な手段は,勤務医の多くが日医に加入して,これを通じての政治的影響力を持つことであろう.すでに,開業医中心というイメージの日医では,その力に陰りが指摘されている.勤務医こそが,現場の窮状を正しく伝え得る主体なのである.勤務医中心の日医なら,国民のイメージを変えられるのではないだろうか.そのためにも,日医は,国民に責務を負う専門職域団体として,会員に高い倫理性を保持させ,厳格な自浄機能を持つ必要があり,また,医師一人ひとりが一層のインフォームド・コンセントの充実に励み,医療への信頼回復に努めることが求められる.
歴史的に,労働者が自己を防衛する主要な手段は二つである.一つが職場の放棄であり,もう一つが職域の団結である.無言の立ち去りは,今日までの努力を無にしてしまうほか,医師の職業倫理の低下といった,本質を見誤った批判にもつながりかねない.医療に対する統制が強まり,海外からの医療労働力の大量輸入といった暴論さえも現実味を帯びる.今こそ,選択の時である.日医と学会が,開業医と勤務医が一体となって医政活動に参加し,国民の,患者の,そして自らの未来のために,正論を展開していくべきであろう.
[ふるかわ・としはる:慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)・医学部外科/TMI総合法律事務所(弁護士)]
|