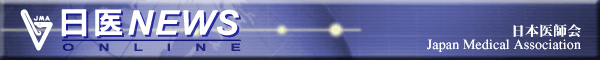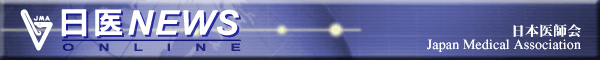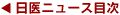 |
第1179号(平成22年10月20日) |

地域で看取る
十和田市立中央病院事業管理者 蘆野吉和

病院で迎える死
一九七八年四月,私が医学部を卒業し,医師免許を得て臨床の現場に立った時,教えられたことは“看取らない”ことの大切さであった.まだ,自宅で亡くなる人が五〇%以上だった時代で,延命治療も進んでいない時代のことである.
それから約十年間は,医学が飛躍的に発展した時代で,延命に役立つ薬剤や医療機器が登場し,医療者は一秒でも長く生命を延ばそうと必死になっていた.
病院で亡くなる多くの患者は,さまざまな薬剤が投与され,気管内挿管,時に人工呼吸器が装着され,心肺蘇生も積極的に行われていた.延命治療が行われ,死が確定するまでの間は家族との温かい触れ合いはなかった.臨終時は医師と看護師が主役で,家族が後ろで不安そうに見守る光景がよく見られた.心電図が平坦となった瞬間に,医師が死の三徴候を確認し,死亡が宣告され,家族は“大切な人”の死を受け入れる余裕もなく,退院の準備をしなければならなかった.
このような死の迎え方,延命措置,病院死が社会的な問題となったのが一九八五年頃からで,終末期医療に対する関心は少しずつ高まり,現在は緩和ケアとして広く社会に認知され,終末期がん患者では,延命措置は多くの場合行われなくなった.しかし,死の迎え方に対する考え方は,まだあまり変わっていない.
“看取ること”の大切さ
死の迎え方に関する私の考え方が変わったのは,がん終末期の在宅医療に取り組むようになってからである.
一九八七年から始めた在宅医療,現在では「在宅ホスピスケア」と呼んでいるが,この経験が私に多くの学びをもたらした.病院で死を迎えること,臨終の席に医師や看護師が同席することを当然と考えていた私が,自宅での死,医師や看護師が同席せずに家族だけで臨終を迎える場面を多く経験することで,“看取り”の言葉の意味(「病人の世話をする」「看病する」「臨終に付き添う」など),家族だけでなく,私たち医療者も看取りから学ぶことが多いこと,看取ることの大切さ,そして家族の看取りを支えることの大切さを実感した.
“地域で看取る”支援体制の整備に向けて
そして,“死”,特に自然の経過と考えられる“死”は医療の問題ではなく,地域社会の問題であること,死を病院から地域に開放することが,地域社会にとって非常に重要なことであり,地域で看取るための体制づくりが必要であると認識するようになった.
そこで,一九九四年頃より,“地域で看取る”ための“地域緩和ケア支援ネットワーク”づくりに取り組み始めた.当初は福島県いわき市で約十年間,二〇〇五年十一月に勤務先が変わってからは,十和田市で約五年間取り組んでいる.
いわき市では,私の所属する外科においては,がん死亡者の約五割が自宅に戻り,約三割が自宅で家族と最期の時を過ごす形となった.また,十和田市では,がん死亡者の約四分の一が自宅あるいは居宅(高齢者専用賃貸住宅)で最期の時を迎える形となっている.
この在宅死を支える地域の体制は,医療支援チームとしての私を含む勤務医と訪問看護ステーションの看護師,保険薬局の薬剤師,生活支援チームとしてのケアマネジャー,各種福祉サービス事業者の担当者,そしてヘルパーで構成される地域緩和ケア支援チームで行っている.
“地域での看取り”を支える勤務医の役割
地域での看取りを普及させるためには,自宅や居宅,あるいは介護福祉施設での看取りを支援するかかりつけ医および訪問看護師の存在が不可欠であるが,十和田市のように訪問診療を行う開業医が非常に少ない地域では,病院の勤務医が訪問診療を行い,地域での看取りを支えることも必要である.
しかし,一般的には,勤務医の役割は,「前方支援」として,がん終末期患者を含め“自然の経過として死を迎える”ことが予測される人を,早めに地域の医療機関に紹介すること,患者や家族に在宅医療の情報を早めに提供し,多少元気なうちに在宅を勧めること,今後の予期出来る病状の変化について,出来るだけ事前に説明しておくこと,そして,「後方支援」として,緊急時の入院を保障すること,病院でも看取りが出来る体制をつくることである.
さらに,出来るだけ家族だけで看取るよう指導すること,生体監視モニターはつけず,家族がケアに参加出来るように配慮すること,家族に対して温かみのあるケアを提供すること,また,十分な症状緩和治療を行うことも大事なことである.
|