日本医師会定例記者会見 6月5日


渡辺弘司常任理事は、松本吉郎会長より諮問「地域に根差した医師の活動である学校医活動を推進させるための具体的な方策は何か」を受けて取りまとめた答申を、5月22日に学校保健委員会の松村誠委員長(広島県医師会長)から松本会長に提出したことを報告するとともに、学校保健委員会で作成した書籍『学校医のすすめ』についても、その概要を説明した。
本答申は、(1)はじめに、(2)第1章 学校医活動の担い手を増やす、(3)第2章 学校医の心構え、職務、(4)第3章 「チームとしての学校」の推進、(5)第4章 中長期的な課題、(6)参考資料、(7)あとがき―で構成されている。
同常任理事は、(2)について、学校医活動は本来「やりがいのある仕事」であるものの、現在、学校医を引き受ける医師が不足するという問題が多くの地域で起きていることを受け、具体的な解決策として、①若い医師や医学生に対しては、研修や医学教育を通して学校医について理解してもらい、新たな担い手を増やす②現学校医に対しては学校医活動へのモチベーションアップとして、質の向上のための学校医研修会を開催する―ことが挙げられていると説明。また、医学生に体験型の機会等を設けることも、新たな学校医の担い手を増やすことに有用との考えが示されているとした。
(3)では、学校医としての活動を支える知識や経験を得るための研修や制度として、①定期的な研修会の開催②地域の事情に合わせた認定学校医制度③教職員に対する労働安全衛生管理―に関する提言がなされていることを紹介。学校医は児童生徒の健康診断や保健指導だけでなく、学校環境衛生に関する指導や教職員の健康管理など、その業務は多岐にわたることから、産業医の配置促進の取り組みと連携していく必要性が指摘されているとした。
(4)では、特に近年注目されている児童生徒の問題行動への対応について「チームとしての学校」で関わっていくことが大切であるとして、①学校内の連携②他の医療関係者との連携③問題行動への対応④地域との連携―の各項目に分けて言及していることを説明。学校医が「チームとしての学校」に積極的に参画することにより、地域に根差した活動がより充実したものとなり、地域社会に貢献できるとの考えが示されているとした。
(5)では、学校保健の観点から今後注力していくべき目標が提言されている他、中長期的な課題として、①健診項目の見直し②PHRの推進―が取り上げられているとした。
続いて、学校保健委員会が作成した書籍『学校医のすすめ』について紹介した同常任理事は、昨今、「学校医の負担が大きすぎる」「学校医のなり手がいない」という声もたびたび聞かれる中、「学校医とはどういうものか」という疑問や不安を解決する足がかりになるような書籍が必要であると考えたと本書を作成した経緯を説明。「学校医の活動がいかにやりがいがあり重要であるか、学校医の魅力が伝わる冊子となった」と述べるとともに、読みやすく分かりやすい書籍とするためのさまざまな工夫が凝らされているとして、同答申と併せて本書を活用することにより、今後も地域に根差した学校医活動の発展に寄与していく姿勢を示した。
なお、本書は、日本医師会員は日本医師会ホームページのメンバーズルームから無料でPDF版の閲覧が可能となっている他〔会員以外の方は有料で購入可能:3850円(税込)〕、11月9日に宮崎県で開催される全国学校保健・学校医大会の参加者にも配布予定となっている。
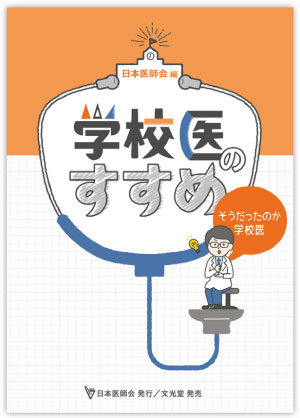
関連資料
問い合わせ先
日本医師会健康医療第一課 TEL:03-3946-2121(代)



