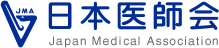医の倫理の基礎知識 2018年版
【終末期医療】C-1.終末期医療の在り方
長尾 和宏(長尾クリニック院長)
医療の発展に伴い「どこからが終末期」なのか分かりにくくなっている。たとえば余命1か月と宣告された末期がん患者が分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が著効して数年以上生きることがある。また認知症終末期で徐々に経口摂取が低下した人に胃ろうを造設した結果、5年以上寿命が延びることもある。これまで「終末期」は医学的に定義できるという前提で議論がなされてきたが、これからは後述するACP(Advance Care Planning)を病棟カンファレンスやケア会議で話し合うべきだ。死期が迫った時期とは病態により異なるが概ね3か月ないし1~2週間だろう。終末期を経て死に至る人は95%で、急病や事故や災害で急死する5%の人ではこの問題はない(厚生労働省:平成27年人口動態統計月報年計)。
延命治療という言葉があるがそもそも医療の大半は延命目的である。限られた生命の中で少しでも寿命を延ばすために医学・医療が存在する。そのため続々と延命治療の選択肢が繰り出される。わが国では人生の最終段階の医療に関して口頭で意思表示をしている人は約7割だが、リビングウイル(LW)として書面に記している人はわずか2~3%に過ぎず欧米と比較して一桁低い。そもそも日本人は自身の終末期医療に関して自己主張をあまりしない。本人と家族が一体となり、時には家族だけで意思決定をする文化である。また認知症や事故で本人の意思が不明な事態が急増している。日本は家族の権限が大きいので本人の意思だけでなく家族にも充分に気を配らなければいけない。ここに日本の終末期医療の最大の特徴と難しさがある。
さて「尊厳死」とはLWを尊重して終末期に延命治療を差し控えるとともに充分な緩和ケアを受けた先にある自然な最期である。差し控えるとは、種々の延命治療の「不開始」ないし「中止」である。「不開始」は自然死や平穏死とも呼ばれている。一方、日本老年医学会などの医学会の終末期ガイドラインに従い、終末期に胃ろうなどの延命治療を徐々に中止することがある。数年前、超党派の議員連盟においては主にこの「中止」についての議論がなされた。尊厳死は法律的には明確に規定されていないが、在宅看取りの大半が尊厳死であることから社会的には容認されているとも考えられている。
一方、「安楽死」(積極的)とは余命とは関係なく激しい苦痛に悩まされている人に致死薬を投与して死に至らしめる行為で、一定の条件を満たさないと医師は殺人罪に問われる可能性がある。「尊厳死」と「安楽死」は別物であるがよく混同される。脳腫瘍で余命半年と宣告された米国の29歳女性が「恋人の名前が言えなくなる前に死にたい」と自宅で薬を飲んで亡くなった。これは自殺であり安楽死である。しかし多くの日本メデイアは「尊厳死」と誤報した。「安楽死」には2種類ある。医者が患者に直接注射や点滴をして死に至らしめる場合と、彼女のように致死薬を処方され自分で飲む場合(医師の支援を受けてなされる自殺(physician-assisted suicide;PAS))があり、前者は100%死ぬが、後者は錠剤をもらっても実際には飲むのは半数以下とのことだ。最近、脚本家の橋田壽賀子氏らが書籍やメデイアで安楽死を主張している。そして7~8割の日本人が安楽死に賛成と答え安楽死議論が活発化している(朝日新聞:死生観の世論調査.2010年11月4日朝刊)。しかし尊厳死としっかり区別しないと議論が混乱する。
多くの国民の願いであろう尊厳死は本人の意思と緩和ケアによるQOL(生活、生命の質)確保が大前提となる。今後、我が国の終末期医療は療養の場を問わずACPが主軸となる。家族と多職種で何度も話し合うプロセス重視の意思決定方法である。日本は和の文化であることと合致する。その核となるのはもちろんLWである。本人意思の尊重は世界各国の生命倫理の共通基盤である。しかしACPは決して万能ではなく、画一的・形式的ではなく個別性を重視して実施されるべきだ。各医学会の終末期ガイドラインに従いながらACPを重ねてQOD(死の質)を高めるという「日本型の意思決定プロセス」を模索する必要がある。
(平成31年3月15日掲載)
目次
【医師の基本的責務】
【医師と患者】
【終末期医療】
【生殖医療】
【遺伝子をめぐる課題】
【医師とその他の医療関係者】
【医師と社会】
【人を対象とする研究】