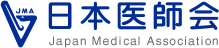医の倫理の基礎知識 2018年版
【生殖医療】D-1.親子の関係をめぐるDNA検査
水野 紀子(東北大学大学院法学研究科教授)
DNA検査によって親子関係の有無はきわめて高い確率で判断できるようになった。しかし民法の定める法律上の親子関係は、遺伝子上の親子関係と必ずしも一致しない。それは民法がDNA検査のない時代に立法されたからではなく、もともと法律上の親子関係とは、遺伝子上の親子関係のみならず子の福祉などを考慮して設計される前提のものだからであり、日本民法がモデルにした西欧法でも、DNA検査が発達した現在もその前提は崩されていない。遺伝子上の親子関係は本人すらアクセス制限がかかるプライバシー中のプライバシーとして裁判所の許可のないDNA検査自体を禁止している国(フランスなど)もあるが、日本と同様にDNA検査が可能な国でも、検査結果で法的な親子関係が覆るとは限らない。
民法の条文は、判例によって解釈上一部変更されているが、その修正を含めた現在の民法の実親子関係決定方法は、次のようなものである。まず母子関係は分娩によって決定され(最高裁昭和37年4月27日判決・民集16巻7号1247頁)、母子関係を基準として、懐胎時に母が婚姻している嫡出子は、父は民法772条の定める嫡出推定により母の夫とされ、母が独身である非嫡出子は、民法779条により、父はその子を認知した男性とされる。
遺伝子上の親子関係と法律上の親子関係が異なる例としては、まず非嫡出子が成年になっていると、民法782条によって、たとえ実の父であっても、子の承諾がなければ、父はその子を認知できない。また嫡出推定は、「推定」という表現にもかかわらず、実際には嫡出父子関係の決定方法を定めるものであって、嫡出推定を覆すためには、夫のみが子の出生を知ったときから1年以内に提起できる嫡出否認の訴えによらねばならない。もっともこの提訴要件はあまりに厳しいものなので、判例は、外観説という解釈論を採用し、子を懐胎した時期に夫婦関係が破綻していた等、外観から見て夫の子ではあり得ない場合には「推定の及ばない子」として、提訴要件の縛りがない親子関係不存在確認請求によって覆せるとする。
母と夫と実の父の三者の間で合意が出来れば、懐胎時期に夫婦関係が破綻していたと外観説に沿うように証言することによって家庭裁判所の審判で戸籍を訂正することも可能であるが、合意が出来なかった場合には、母と夫の婚姻関係が破綻して夫婦が離婚していても、夫との父子関係は否定できない。実際に、母と実の父によって育てられている子が夫との父子関係を否定することを求めた事件で、最高裁平成26年7月17日判決・民集68巻6号547頁は、DNA鑑定によって血縁関係のないことが判明していた夫との父子関係を外観説によって維持した。この判決に付された山浦判事の補足意見は「DNAは人間の尊厳に係る重要な情報であるから決して濫用してはならない。たまたまDNA検査をしてみた結果、ある日突然、それまで存在するものと信頼してきた法律上の父子関係が存在しないことにつながる法解釈を示すことは、夫婦・親子関係の安定を破壊する」と説明する。
さらに、事実上の養子を実子として届出る、いわゆる「藁の上からの養子」(産褥の場からもらい受けた子との意味)は、母子関係を偽るものであるため親子関係不存在確認請求訴訟で覆すことができるが、この場合についても、最高裁平成18年7月7日判決・民集60巻6号2307頁は、親子関係不存在確認請求訴訟を権利濫用で封じた。
強制認知のように、親のない子が親を求める場合はともかく、すでにある親子関係を否定する場合には、DNA鑑定の利用は慎重でなければならない。法律上の親子関係は認められなくとも遺伝子上の親を知りたいという要求は、たとえばAIDのような生殖補助医療で出生した子から、出自を知る権利として強く主張される。一方、法律上の親子関係と異なる出自であるという事実を知ったAIDによる出生子が大きな苦悩を抱えるように、DNA検査によって安易に出自を知らされない権利にも、配慮が必要であろう。
(平成30年8月31日掲載)
目次
【医師の基本的責務】
【医師と患者】
【終末期医療】
【生殖医療】
【遺伝子をめぐる課題】
【医師とその他の医療関係者】
【医師と社会】
【人を対象とする研究】