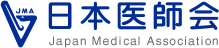医の倫理の基礎知識 2018年版
【生殖医療】D-4.代理懐胎と倫理
久具 宏司(東京都立墨東病院産婦人科部長、前東邦大学医学部教授)
1978年、世界で初めて体外受精が成功し、1つの生殖現象に2人の女性が関与することが可能となった。体外受精によって行われる代理懐胎が、IVF surrogacy、 full surrogacy(体外受精代理懐胎)で、すなわち、多くは配偶者間の受精卵(胚)を第三者の子宮に移植して出産してもらうわけである。しかしそれ以前から人工授精型の代理懐胎(partial surrogacy;サロゲートマザー)が可能であり、既に欧米で行われていた。この項では現在の大勢を占めるIVF surrogacyにおいて考えられる倫理的問題点を考察する(以下の文中の代理懐胎はIVF surrogacyである)。
代理懐胎が、通常の体外受精妊娠に比し高いリスクを伴うか否かという点に関して、十分なエビデンスを有するデータは現時点では示されていない。一方、不妊女性が他人から卵子の提供を受けて妊娠・出産する卵子提供妊娠では、妊娠性高血圧、妊娠第1、2三分期における異常出血、胎盤構築の異常の発生が有意に高いことが、多くの臨床研究やそれらのレビューから明白となっている。代理懐胎は依頼女性と懐胎女性の関係が卵子提供妊娠とはちょうど逆になっており、懐胎女性が胎児と遺伝的相同性を全く持たないという点は代理懐胎と卵子提供妊娠に共通である。したがって、代理懐胎においても、卵子提供妊娠と同様のリスクの存在が推測される。ただし、懐胎女性が卵巣機能に障害を有しない点で、代理懐胎におけるリスクはより小さいとも考えられる。
そもそも妊娠・分娩はさまざまなリスクを伴うものであるが、その妊娠・分娩を他者に依頼し、10か月間その子宮を"借りる"ことの是非こそが倫理的に問題となる。この10か月間、懐胎女性は胎児をただ預かっているだけではなく、胎児との間には胎盤を介して物質の移動が起こり、それは胎児に出生後長期にわたる影響を与えるかもしれない。また、この10か月間に懐胎女性には母性が芽生え、母乳哺育の準備など身体的にも育児に向けた準備が整い、生まれてくる児を慈しむ感情が湧くであろう。しかしながら、懐胎前の契約により、出産後に懐胎女性は児から引き離されるのである。この局面で児の引き渡し拒否などの事例が海外では少なからず起こっている。児に何らかの異常がみられた場合に、出生後に依頼者側が児の引き取りを拒否する例も見られる。早産により生まれた超低出生体重児に対する治療を、発育後に出現する可能性のある後遺障害を理由に、依頼者側が拒否する事例も発生している。懐胎している女性は医療者との間の診療の契約によって診療を受けているが、それとは別に、懐胎女性は依頼者との間に代理懐胎の契約を結んでいる。この契約に基づいて取られる処置は臨床医の通常の判断と同じとは限らず、救命されるはずの命が見捨てられるなど、児の生命や予後が顧みられないことがある。
代理懐胎は、10か月間子宮を"貸す"行為という性質上、そこに対価が発生しやすいこと、またその対価を期待する商行為(ビジネスに誘引すること)に発展する可能性を秘めている。一方で、代理懐胎を依頼する、または引き受けることは自己決定による行為であり、その権利を侵害されるべきではない、との見方もあり、代理懐胎契約を相互扶助による生殖医療とする主張も存在する。このような見方に立つと、代理母になることは労務とみなされ対価が支払われるか、または奉仕であっても報酬が支払われることになる。代理懐胎が容認されている地域においては、代理母を女性の収入源の1つとみなし、その契約を仲介する業者も含めてビジネスとして大きな市場を形成している。しかしながら、社会的・倫理的にみると、商行為の有無に関わらず、代理懐胎においては、自身の体を他人の生殖行動の道具として利用される懐胎女性が搾取されているとする考え方が強い。
代理懐胎の対象となる女性、すなわち"適応"をどのように設定するか、という点も考慮されなければいけない。先天的な子宮の欠如、または疾患の治療のために子宮摘出を受けた女性は絶対的適応とみなされる。他に、子宮を有している相対的適応もあり、体外受精不成功例、合併症による妊娠困難例、習慣流産例が含まれる。絶対的適応に限るとしたら、そのように限定することの合理的根拠の有無、相対的適応を含めるとしたら、適応症例の基準設定の妥当性および現場医師の判断が重要となろう。このような問題を考えるに当たっては、代理懐胎の施行により婦人科疾患治療において子宮摘出に踏み切るハードルが下がる可能性、自身で妊娠せずに自分の子どもをもちたいと考える女性の存在など想定外と思えるような事態も視野に入れておく必要がある。
代理懐胎では、懐胎女性が自身と遺伝的つながりのない児を出産することから、生まれた子の母親を法的にどのように定めるのか、問題となる。分娩者を母とする従来の考え方を代理懐胎にも適用し、懐胎・分娩した女性を子の母親とした後に、依頼者と子の間に養子縁組を認める国(フランスなど)がある一方、懐胎者の妊娠中に裁判所の審理により依頼者を子の母親と認定することを妨げない地域もある。アメリカ合衆国のネバダ州で代理懐胎を依頼し、現地の懐胎女性が出産した子を日本に連れ帰った日本人女性が、ネバダ州裁判所の決定により子の母親をこの日本人女性とした出生届が、日本の役所で受理されない事案が発生した。この女性が、自身が子宮摘出を受けたこと、アメリカで代理懐胎を行い、子を得る予定であることをマスコミを通じて広く公言していたことから、出生届が不受理となったものである。裁判を通じて争われたこの事案は、最高裁において、外国判決の承認という論法を退け、本件の外国判決がわが国において公の秩序に反するものとして、この女性の訴えを棄却した。最高裁の2007年のこの決定は、「母子関係は、分娩の事実により当然発生すると解する」とした1962年の判例を改めて確認したことになる。最高裁は、本事案において、依頼者夫婦と子の間に特別養子縁組を成立させることが可能で、子の福祉にもかなう、と付言した。わが国には現在、代理懐胎を含めた生殖補助技術を規定する法は存在しないが、過去の判例と特別養子縁組制度により、フランスなどと同等の運用をしていることになる。
古来より生殖現象は男性と女性の間において営まれるものであり、当然とも思えるこの摂理に対して疑問を差し挟む余地はなかった。しかしながら、近年、男女の性別という概念が揺らいでいる。もっともこの概念の変化は新たに生まれたものではなく、多様性を尊重するという今日的な価値観に促されて、これまで隠れていたものが表面化しただけかもしれない。男性同士、女性同士によるパートナーシップを公的に認める自治体が日本においても現われ、海外では同性婚を容認する国や地域が少しずつではあるが、増えている。LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)の者たちが差別されることのない社会が、世界的にみて広がりつつある。また、性同一性障害(性別違和)は治療の対象と認められ、生殖器への手術を受けることにより、戸籍の性別を変更することが日本で可能となった。
このような、従来想定されていなかったカップルが認められる社会で、これらのカップルが子をもちたいと考えるのは必然のことであろう。また、カップルでなく、男性・女性、それぞれが独身であっても子をもちたいと考えることもある。このような時に、養子ではなく、自分の配偶子(精子・卵子)を使用することを希望する場合には、代理懐胎、および精子提供、卵子提供の技術を用いて自分の遺伝子を受け継いだ子をもつことが可能である。日本で、性同一性障害に対し手術を受けて女性から男性になった者が女性と結婚し、他の男性から精子提供を受けて子をもうけた事例で、その子をこの夫婦の嫡出子と認める最高裁判断が下された(2013年)。海外からは、代理懐胎によってゲイカップルが子をもった事例が報道されている。代理懐胎を含む生殖補助技術(Assisted Reproductive Technology;ART)は、もはや不妊治療の延長線上に存在するのではなく、子をつくるための生殖行動の選択肢の1つとして位置づけておく必要がある。日本では、2018年現在、日本産科婦人科学会の見解により、代理懐胎はできないことになっている。代理懐胎が容認された場合、不妊治療を超えた上記のような事例でのニーズも高まることは容易に予見しうる。
欧米では代理懐胎について許容または禁止を法により明確に定めている国や地域がある。個人の自己決定権を代理懐胎においてどの程度尊重しうるか、国民的議論を重ねた末に決定されたものであるが、その過程で宗教的な価値観や倫理観が与えた影響は少なくないと推定される。日本において多数を占める仏教では、煩悩や欲望など精神世界への介入が主であり、人の存在、特に生命の始まりについての示唆は少ない。また、日本では思考の拠り所として宗教をあまり重視しない傾向があり、代理懐胎を含む生殖医療の問題で宗教界をはじめとした倫理学的な意見が出にくい状況があると考えられる。
代理懐胎の倫理を考えるうえでは、依頼者の願望、懐胎者の安全、生まれてくる子の福祉、三者とも等しく尊重されなければいけない。特に結果として誕生する子については特段の配慮が必要である。依頼者、懐胎者は自己決定に基づいて代理懐胎を行うのであるが、生まれてくる子は、当然ながら自己決定はできない。子が親の付属物ではなく、親と対等な一個の人格であることを改めて認識することが重要である。
参考文献
- 1)櫻田嘉章,町野 朔,西希代子他:生殖補助医療と法,学術会議叢書19,日本学術協力財団,東京,2012.
- 2)日本宗教連盟:「代理出産」の問題点を考える-生殖補助医療といのちの尊厳.第5回宗教と生命倫理シンポジウム報告書,日本宗教連盟,東京,2011.
- 3)林かおり:海外における生殖補助医療法の現状―死後生殖,代理懐胎,子どもの出自を知る権利をめぐって.国立国会図書館調査及び立法考査局,外国の立法,2010;243:99-136.
- 4)日比野由利:ルポ生殖ビジネス―世界で「出産」はどう商品化されているか.朝日新聞出版,東京,2015.
- 5)久具宏司:生殖医療にかかわる法的問題―代理懐胎.あなたと患者を守る! 産婦人科診療に必要な法律・訴訟の知識,臨婦産 2017:71(12):1165-1173.
- 6)金子 昭:生殖倫理の現況と展望―日本人の宗教観と生殖医療.医のあゆみ 2017;263(11,12):977-980.
(平成30年8月31日掲載)
目次
【医師の基本的責務】
【医師と患者】
【終末期医療】
【生殖医療】
【遺伝子をめぐる課題】
【医師とその他の医療関係者】
【医師と社会】
【人を対象とする研究】