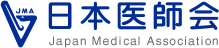医の倫理の基礎知識 2018年版
【終末期医療】C-2.生命維持治療の差し控え、中止
樋口 範雄(武蔵野大学法学部特任教授、東京大学名誉教授)
1.生命維持治療の差し控え、中止の問題が論じられて久しい。そもそもこの問題が顕在化したのは、生命維持治療なるもの、典型的には人工呼吸器によって自発呼吸のできなくなった人を救う(という意味は、生命だけを維持する)医療技術の進歩が起こったからである。
アメリカでは、1960年代から70年代にかけてこのような技術が知られるようになり、カレン・クインラン事件をはじめとするいくつかの有名な訴訟や、自然死法その他の名前で知られる法律の制定、その一方で、インフォームド・コンセントや自己決定、さらに生命倫理4原則など医療倫理の浸透によって、現代では基本的な考え方が固まっている。それは、終末期または植物状態に陥った患者が、真摯な自己決定によって治療を拒否するならそれを尊重するのが、医療倫理に照らしても正しく、法的に見ても適切だという考えである。言い換えれば、「生命維持治療の差し控え、中止」はもはや法律問題とはされていない。
これに対し、医療技術の進展では遜色のないわが国では、相変わらず、次のような見解が時に表明される。
「人工呼吸器の取り外しは、殺人罪に当たるおそれがある。たとえ本人の同意があっても、嘱託殺人罪に当たるおそれがある」。
だが、実際に、人工呼吸器の取り外しだけで起訴された例はない(横浜地裁の事件や川崎協同病院事件が喧伝されているが、いずれも筋弛緩剤の投与までに至った事例であり、延命治療の差し控えや中止に関する判例の言及も、法的にいえば「傍論」に過ぎない)。いわんや有罪とされたこともない。もしも法律の世界にも evidence based law があるのなら、上記の言明には実は一切証拠はない。それにもかかわらず、どうしてわが国ではいつまでもこのような議論が続くのかという点こそが問題である。そこには医療の側の問題があると同時に、法の側にも問題がありそうである。
2.アメリカでは、1960年代に人体実験と呼ぶべき臨床研究が明るみに出され、それを契機として、生命倫理・医療倫理のあり方が国家レベルで議論された。そのようななかで、生命倫理4原則が生まれた。4原則とは、Non-maleficence = Do no harm(無危害)、Beneficence = Do some good(善行)、Autonomy(自己決定・自律)、そしてJustice(配分的正義)である。このうち、特に、治療のあり方は自らの身体に関わる問題であること、しかも植物状態のような状況で生きていたいかなど、何が自らの生き方・死に方であるかについても「自己決定」し、患者に治療拒否権を認めることこそ倫理的だとする考えが強くなった。医師が、これがあなたにとって最善だと容易に決めることのできない状況がその背景にある。むしろインフォームド・コンセントという考え方が強調されて、医師は患者の自己決定を助けるような重要な情報を提供し、それを基に治療の打ち切りや差し控えを決めるのは患者本人だとされるようになった。
他方、法の場面でも、これらに対応して重要な動きがあった。1976年のカレン・クインラン事件では、ニュー・ジャージー州最高裁が、植物状態患者の人工呼吸器を外す権限を後見人たる父に認めた。同じ1976年のカリフォルニア州法を皮切りに、自然死法やリビング・ウィル法と呼ばれるような法律が制定され、自らが「自然に」死にたい(医療技術だけに頼って、単に生命を維持されている状態では生きたくない)と考えればそれを尊重することが認められるようになった。
さらに1983年のバーバー判決では、人工呼吸器の取り外しも栄養・水分補給の停止も刑事犯罪にならないと明確に述べられた。その結果、生命維持治療の差し控えはもちろん、中止をしても、医師が訴追されるおそれは全くなくなった。自らの身体に関する決定権は本人にあるという考えが、倫理的にも法的にも認められたことになる。
3.これに比べると日本の状況はこの40年ないし50年何ら変わっていないようにみえる。インフォームド・コンセントという言葉こそ人口に膾炙されるようになったが、それが仮に死を招く場合であっても、治療を拒否できる権利まで含むとは考えられていない。これだけ同意書にサインを求められるようになって、自己決定が尊重されるようになったはずなのに、実際には、医療のパターナリズムや、法の旧態依然たる解釈(殺人罪や嘱託殺人罪が定められた刑法は、このような医療技術の発展を想定していないわけであるから、刑事法本来の限定解釈の原則や謙抑性からすれば、そのような犯罪になるわけがない状況でも、形式的な法解釈で、殺人罪に当たる「おそれ」があるとする態度)が残っている。生命倫理4原則も、わが国のこの分野の学者の間では常識のはずだが、医療倫理の内在的発展も法の現実的対応も未だしという状態である(もっとも、現実には人工呼吸器の取り外しについて裁判例がないという事実が、刑事法の謙抑性という原則が実際には守られているという証拠にはなろう)。
ただし、国民の意識は相当に変わってきた。典型的な例はガンの告知である。30年前なら、告知はされなくて普通だったが、現在では末期ガンでも告知する例が多いと聞く。同様に、終末期医療についても、すべての世論調査で、多数の国民はどこまでも延命治療をして欲しいとは願っていないという結果が出ている。
さらに、この問題は法制化するのではなく、専門学会等のガイドラインによって、現代の医療として適切な程度で生命維持治療の差し控え、中止が行われるのを是としている。その判断について、医師だけで決めないで、可能なら本人の意思、さらに家族が相談して決めてもらいたいというのである。
2007年、厚生労働省はいわゆるプロセスガイドラインを公表し、終末期医療(人生の最終段階の医療)について、多職種の医療ケアチームで判断する、本人の意思・希望の尊重を基本として、本人とその家族等でそれが何かを繰り返し話し合っておくこと、さらに緩和ケアなど終末期医療の質の向上を図ることが今後の方向であると明らかにした。2018年には、実際にそれを行うためのアドバンス・ケア・プランニングが重要であるとガイドラインに明記する改訂がなされた。
現在まで、生命維持治療の中止や差し控えについて、一定の慎重な手続を経る限り、違法ではなく、それに関与した医療従事者の法的責任も問われないという尊厳死法がわが国では制定されていない。だが、実態としては、厚労省や終末期医療に関与する専門学会等のガイドラインがそれに代わる役割を果たし、「人工呼吸器の取り外しは殺人罪に当たるおそれがある」という言明はもはや適切でないとする考え方が広まりつつある。
代わって望まれるのは、超高齢社会を迎え、かつてない多数の死亡者数が今後予想されるわが国において、1人ひとりの高齢患者に、残る時間を有意義に本人の希望に添った生き方(死に方)を実現することを支援するような枠組みを作り上げることである。
(平成30年8月31日掲載)
目次
【医師の基本的責務】
【医師と患者】
【終末期医療】
【生殖医療】
【遺伝子をめぐる課題】
【医師とその他の医療関係者】
【医師と社会】
【人を対象とする研究】