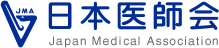医の倫理の基礎知識 2018年版
【医師と社会】G-7.薬剤の副作用とその説明義務
鈴木 邦彦(前日本医師会常任理事)
医療において患者は公正な医療を受ける権利、説明を受け自らの意思に基づき医療を受ける権利など、医療を拒否する権利、セカンドオピニオンを求める権利を有している。医師は何よりも患者の利益を第一に考えて行動することが基本原則であり、これらの権利を害してはならない。
このことは、日本医師会の医師の倫理綱領にも、「3.医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。」ことが肝要であると述べられている。特に薬物治療については、この原則を守ることが重要である。
薬剤は、有効性と安全性のバランスが許容できると判断された場合に国が承認する。添付文書で副作用の注意喚起がなされているが、承認までに得られる臨床データは限られており、市販された後で初めて報告される副作用も多い。承認されて間もない新薬は、副作用の情報について特に注意を払う事が求められ、企業による重点的な情報収集活動も行われている。近年は、従来主流であった低分子医薬品とは異なる作用機序の抗体医薬品を初めとするバイオ医薬品等の新薬も続々と承認され、使用されている。個別化医療の一環で、遺伝子レベルでの治療効果や副作用の起きやすさを患者毎に検討する研究も進められており、また、薬理学的にある程度説明できる副作用もある。しかし、殆どの場合、一人ひとりの患者における副作用のリスクは予測できない。このような薬剤が持つ副作用の特性により、薬剤を適正に使用した場合でも副作用の発生を完全には防ぎきれず、稀に重篤な副作用に発展する場合がある。
薬物治療は日々進化しており、医療者は患者へ適切な説明を行うために、副作用について十分理解し、その情報収集に努めていることが肝要である。しかし、薬剤に関する情報は膨大であり、しかも薬剤を併用した際のリスクは気づきにくいことが多い。患者の治療に当たっては、製薬企業からの情報提供はもとより、院内外の薬剤師からの薬学的知見に基づく提案や、厚生労働省が発行している重篤な副作用の早期発見や予防のための「重篤副作用疾患別マニュアル」(図1)などの活用が考えられる。
図1 重篤副作用疾患別マニュアルの例
| 皮膚 | 薬剤性過敏症症候群など5疾患 |
|---|---|
| 肝臓 | 薬物性肝障害 |
| 腎臓 | 間質性腎炎など6疾患 |
| 血液 | 播種性血管内凝固など9疾患 |
| 呼吸器 | 非ステロイド性抗炎症薬による喘息発作など7疾患 |
| 消化器 | 偽膜性大腸炎など5疾患 |
| 心臓・循環器 | 心室頻拍、うっ血性心不全 |
| 神経・筋骨格系 | 薬剤性パーキンソニズムなど12疾患 |
| 卵巣 | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) |
| 精神 | 悪性症候群など5疾患 |
| 代謝・内分泌 | 偽アルドステロン症など5疾患 |
| 過敏症 | 非ステロイド性抗炎症薬による蕁麻疹/血管性浮腫など4疾患 |
| 口腔 | 抗がん剤による口内炎など3疾患 |
| 骨 | 骨粗鬆症、特発性大腿骨頭壊死症 |
| 泌尿器 | 尿閉・排尿困難、出血性膀胱炎 |
| 感覚器(眼) | 緑内障など3疾患 |
| 感覚器(耳) | 難聴 |
| 感覚器(口) | 薬物性味覚障害 |
| 癌 | 癌 手足症候群 |
厚生労働省:重篤副作用疾患別マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp061122-1.html人がその人にとって最適な選択をする上で選択肢のマイナス面を考慮することは極めて重要であり、薬物治療を受ける患者も同様である。但し、仮に、薬物治療の過程で医療者側が十分な説明を行わなかった場合に発生した副作用については、医師の倫理に反すると捉えられ、責任を問われる可能性がある。患者に対して薬剤の副作用の内容を説明することは、治療方法の選択の機会を保証するという側面のみならず、服薬後に副作用症状が現れた場合に患者自身が早期に医療機関を受診するなど、適切に対処しうるための情報を伝達するという、療養指導としても重要な意味をもつのである。裁判上、このような医師の説明義務が認められた例がある。たとえば、髄膜腫の手術を受けた患者が退院する際に、抗痙攣剤としてアレビアチン、フェノバール等を処方され、その後、発疹が発現したものの、10日ほど経過してから医療機関を受診した。結果として患者は中毒性表皮壊死症(TEN)で死亡しており、裁判所は、処方薬とTEN発症との関連性を前提としつつ、「医師には投薬に際して、その目的と効果及び副作用のもたらす危険性等について説明をすべき義務があるというべきところ、患者の退院に際しては、医師の観察の及ばないところで服薬することになるのであるから、その副作用の結果が重大であれば、その発症の可能性が極めて少ない場合であっても、・・・(中略)・・・副作用の重大な結果を回避するために、服薬中どのような場合に医師の診察を受けるべきか患者自身で判断できるように、具体的に情報を提供し、説明指導すべきである」として、何かあれば受診するようにといった一般的な注意をするにとどまった医師側の過失を認め、遺族に対する慰謝料の支払いを命じた(高松高裁平成8年2月27日判決(判例タイムズ908号232頁))。発生頻度の低いTENの説明義務については、これを否定した裁判例(東京高裁平成14年9月11日判決、判例時報1811号97頁)もあり、議論の分かれるところではある。患者の安全な服薬を指導するという観点からみれば、すぐに医療機関を受診すべき場合など薬剤の副作用をめぐる注意点についてはできる限りわかりやすく患者に伝えることを心がけるべきである。
(平成30年8月31日掲載)
目次
【医師の基本的責務】
【医師と患者】
【終末期医療】
【生殖医療】
【遺伝子をめぐる課題】
【医師とその他の医療関係者】
【医師と社会】
【人を対象とする研究】